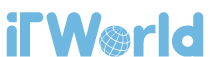みなさんこんにちは!ボラです🍡
今日は最近読了した「それ、すべて過緊張です。」という精神科医である奥田弘美さんの著作で得た知識を基に、みなさんに感想をシェアさせていただこうと思っています。
これからご購入いただく方のためにも、内容について触れすぎることの無いように書きますので、
私の感想が多めになります。
・
「過緊張」について
私は割と常に「どのように動けば今後の自分の人生に良い影響が与えられるか?」を考えたり、
「仕事中のあの回答は、答え方が良くなかったかもしれない」「こういう動き方ができたのではないか」など、仕事での自身の対応や業務について思いを巡らせることが多く、仕事の夢を見ることもしばしば。
この自分の仕事や自身が社会にどのように貢献できるのかを考えること自体はいいところだと思っているのですが、マイルールで自分を追い込んでしまうことも多々あります。
こういった、緊張状態がつづくことを「過緊張」と呼んでおり、こういったタイプに当てはまりやすい性格や、その具体例、対策を紹介していただいている内容です。
・
私はもう紹介されていた「過緊張が当てはまりやすいタイプ」の5つのうち2つにドンピシャで当てはまっていました。
それはそれはもう当てはまりすぎて「私の自己紹介で使える?」と思ったほどです。
これは良しあしではなく、そういうタイプであるといった項目でしたが、あまりにもチェックが付きすぎて、
肩の力が入りすぎてしまっていること、を実感するにつながりました。
・
ただ私がまれなわけではなく、当てはまる方や他のタイプで当てはまる方は多いように思います。
正直、こういったストレスへの向き合い方であるコーピングや、対策と呼ばれるものは「できたらやってるよ」と思われることが多いと思うのですが、本作ではかなり詳細に、というか日々の暮らしに寄り添って書いてくださっています。
・
心を休め、元気な状態でよいパフォーマンスを発揮し続けることは、社会人にとって非常に重要であり、
それに伴う体力や気力がなくて悩んでいる方は多いと思います。
パフォーマンス発揮のために心の安静を保つ、「急がば回れ」のような戦法ですね。
私はこの急がば回れ戦法を大切にしないと、体力が少ないのに走り続けて、倒れてダメにしてしまうリスクが高いと感じたので積極的に休み、心の安静を保ち、趣味を楽しんでいこうと思いました。
・
普段からなんとなく「自分はこういうタイプなんだろうな」と思っていたところを定義化、言語化していただき、対策方法も事例と併せて知ることができたので仕事に向き合う日々の中で読んでよかったと思う本でした。
ので、何者でもないいち社会人のおすすめということで、ぜひ機会があれば読んでみてくださいね。
・
さて、わたしはこの土日で勉強と、ゆっくりすることと、友人との時間を予定しています。
QOLがあがる家用のスピーカーも買う予定なんです。
みなさんはどうやって心を休めますか?
また来週元気に過ごすために、素敵な週末をお過ごしくださいね!